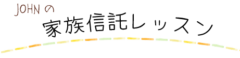家族信託は、将来の資産管理や承継の手段として注目されていますが、相続対策の一環としてよく用いられる「暦年贈与」との組み合わせが可能かどうかについては、正しく理解しておく必要があります。「家族信託を使えば暦年贈与も簡単にできるのでは?」と考える方も少なくありませんが、実際にはいくつかの法的・実務的な制約があります。
まず、暦年贈与とは、贈与税の非課税枠(年間110万円)を利用して、毎年少しずつ資産を移転する方法です。これにより、長期間をかけて相続財産を圧縮し、将来の相続税対策に活用することができます。
一方、家族信託は、財産を信託契約により別の人(受託者)に託し、その財産を管理・運用してもらう制度です。このとき、信託財産の受益者は、その財産から得られる利益を受け取る権利を持ちますが、形式的には財産の所有権を完全に移転したわけではありません。
では、「家族信託を通じて暦年贈与ができるのか?」という問いに対して、基本的には家族信託で暦年贈与を実現するのは難しいと考えられています。なぜなら、贈与とは本来、贈与者が贈与先に対して財産を「渡す意思」を明確に持ち、かつ受贈者がそれを「受け取る意思」を表明することが前提となるためです。
家族信託の場合、贈与者(委託者)が直接資産を贈与するのではなく、受託者を通して運用される構造になっているため、暦年贈与のように「毎年贈与契約を交わす」という形に当てはまりません。そのため、贈与税の非課税枠を適用するための「都度の合意」が成立していないと見なされ、結果として贈与税が課税されるリスクがあります。
たとえば、子ども名義の信託口座に毎年110万円ずつ移すような信託契約を結んだとしても、それが「一括して契約時に定められた内容」であれば、税務署はこれを「定期贈与(複数年にわたる贈与の予約)」とみなす可能性が高く、全額が課税対象とされることもあります。
このように、家族信託と暦年贈与は、それぞれに役割と目的が異なります。暦年贈与を確実に活用したい場合は、贈与契約書を毎年作成するなど、形式面をしっかり整えた上で直接の贈与を行う方法が適しています。家族信託は、むしろ認知症対策や不動産の管理継承など、長期的かつ柔軟な資産運用を目的とするケースに適しているといえるでしょう。
家族信託を使って暦年贈与を行うことは、原則として制度上難しいとされています。暦年贈与には、毎年の贈与者と受贈者の意思確認が必要であり、信託契約により一括して決められた資金移動は、贈与税の課税対象とされるリスクがあります。信託は柔軟な資産管理に向いており、暦年贈与とは使い分けが必要です。目的に応じて制度を正しく選ぶことが大切です。